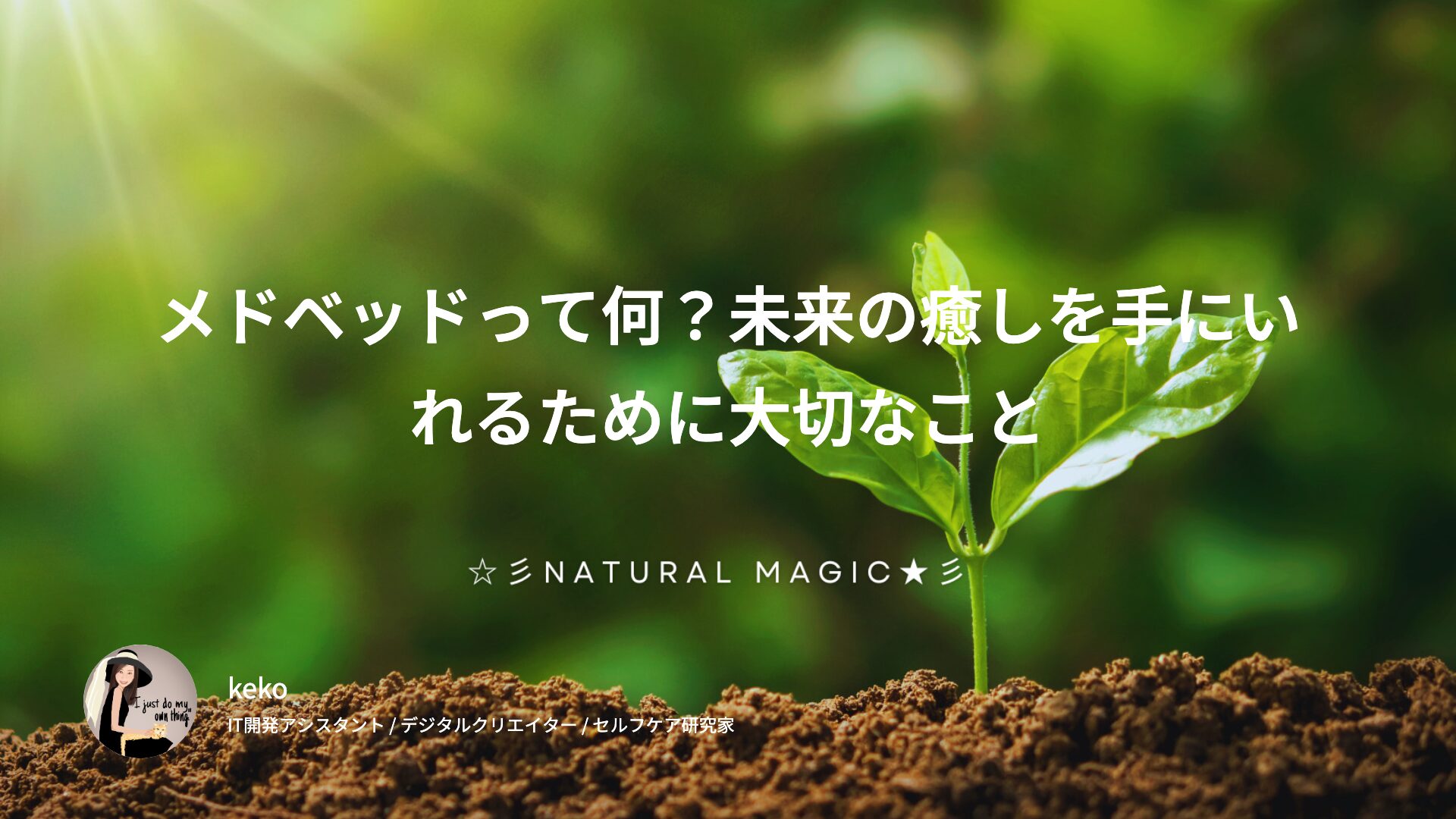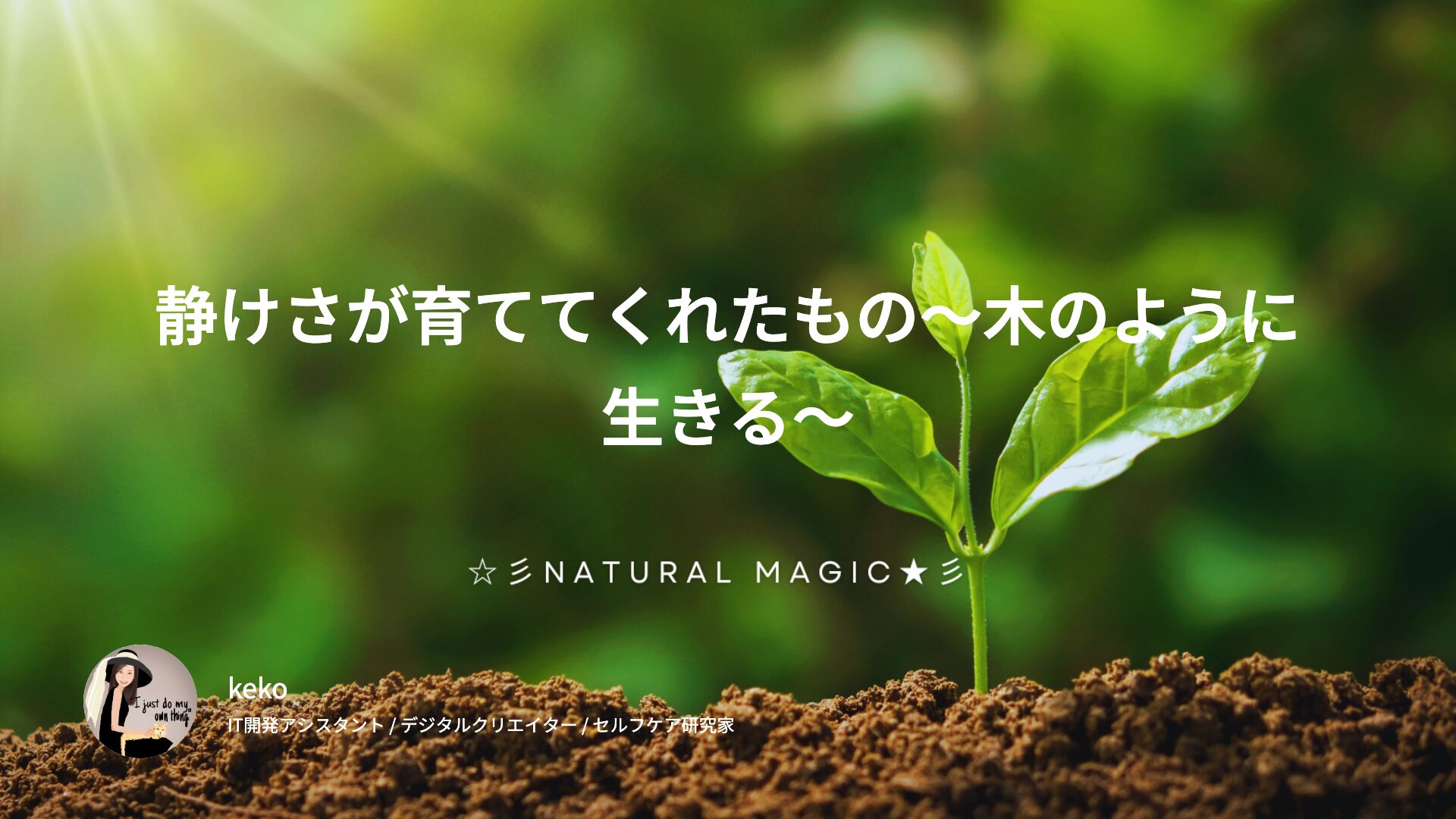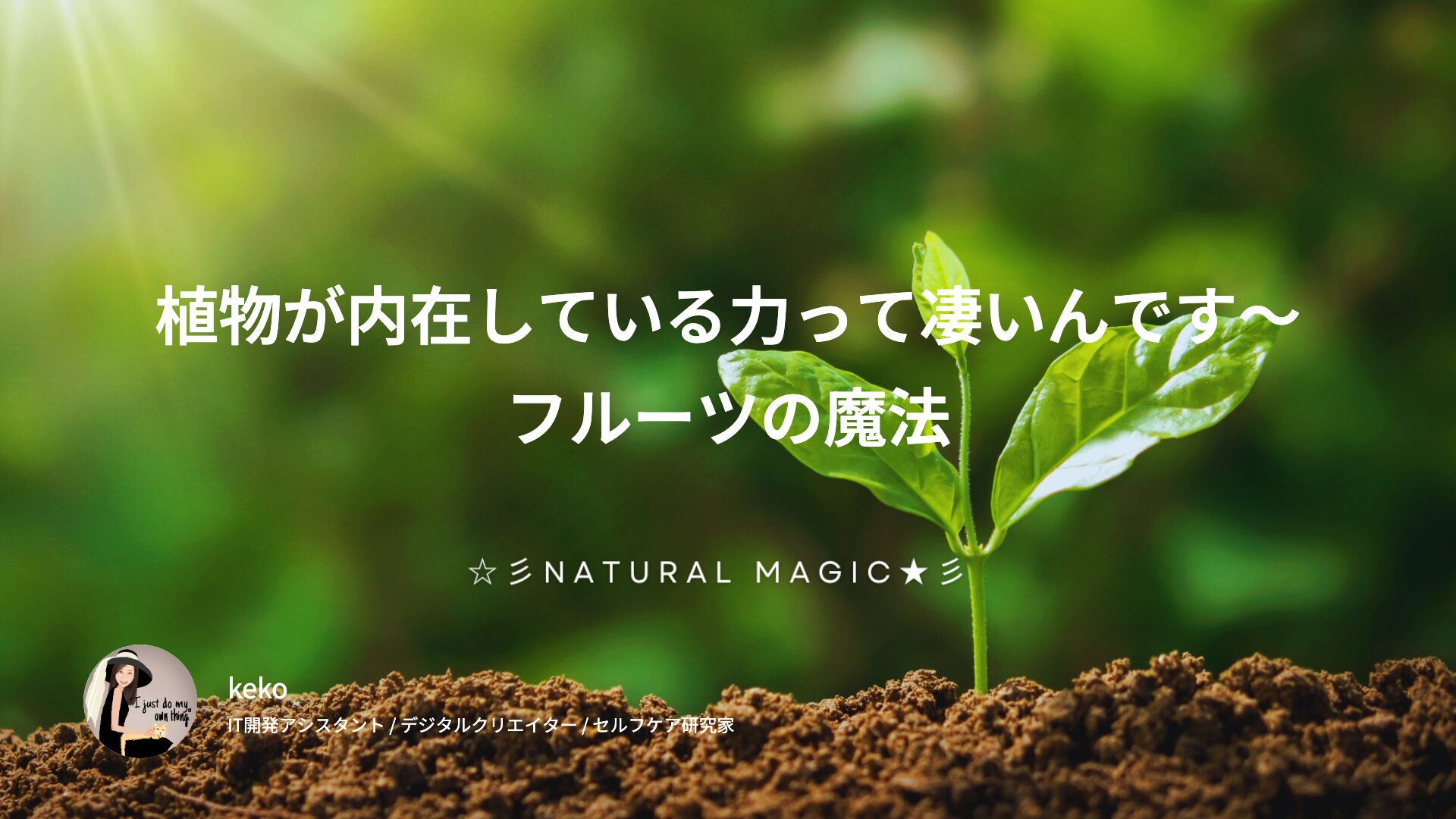「生きている英霊」船坂弘さんから受け取ったもの─不死身の分隊長が遺した“命の使い方”
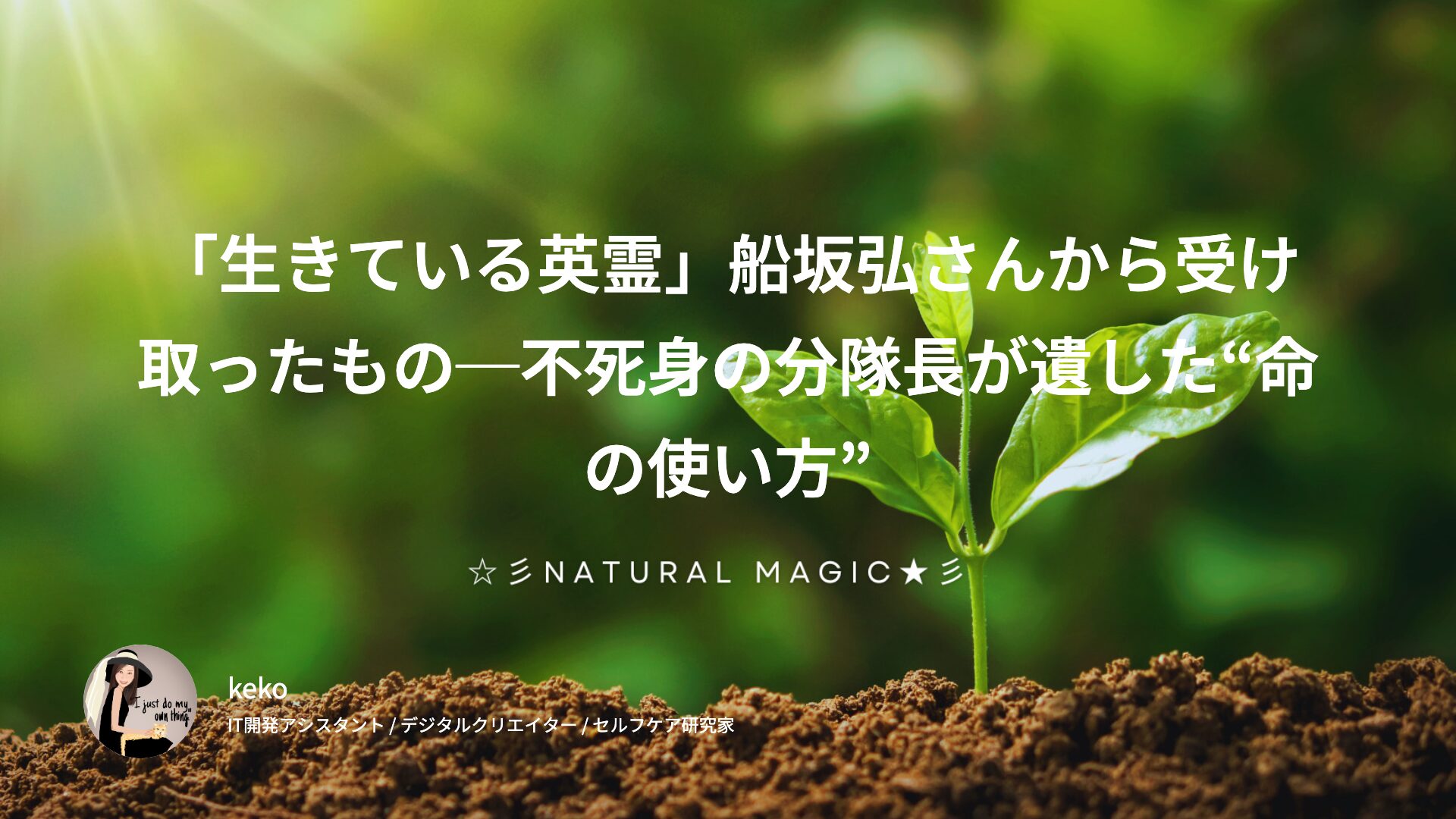
この記事を書いてからしばらく経ちますが、今も船坂弘さんの言葉は、私の中に生き続けています♪
「命の使い方」を、もう一度、静かに考えてみませんか?
朝、メイクを整えながら見た一本の街頭演説。
心に熱が走り、気づけば涙をこらえていた私がいました。

涙の原因はこの動画↓(T_T)↓
その震えは「悲しみ」ではない。「誇り」と「覚悟」に近いもの
語られていたのは、船坂弘(ふなさか ひろし)という、戦後を生きた”真の武士”の物語です。
英霊は「昔の人」ではなかった
彼は太平洋戦争末期、アンガウル島という小さな島で、
たった1200人の守備隊の一人として、2万人超の米軍に抗った。
迫撃砲を撃ち尽くし、傷を負ってもなお、倒れた仲間の弾を自らの体に押し当てて点火し、化膿を防ぐ。
体中に銃創と破片を抱えながら、自決すら果たせず、亡霊のように戦い続けた。
一度は死亡とされながらも、死体安置所で蘇生。
その後も収容所を脱走し、飛行場を燃やそうとすらした。
こんな生き様が、現代に響かないわけがない。
本のデパート、大盛堂書店を創設
戦後、彼はただ“生き残った者”ではなく、未来を築く者となった。
アメリカの先進性を「敵」ではなく「学び」とし、
渋谷駅前にたった一坪の書店を開き、やがて「本のデパート」となる大盛堂書店を立ち上げる。
あれほどの戦場を知った人間が、
戦後に選んだ道が「本を届けること」だったということに、私は深く震えた。
真の“道”を貫いた者
彼は剣道六段、居合道、柔道の達人でもあり、
その精神はまさに“武士道”そのものだった。
三島由紀夫とも親交があり、彼に愛刀を贈った。
しかし、彼の本当の“戦”は、戦後に始まっていたのかもしれない。
慰霊碑を自費で建て、印税を寄付し、
戦没者や現地の人々との和解を進めたその生き方は、
“国のため”を超えて、“命そのものの尊厳”に根ざしていた。
私が涙したのは、“命の使い方”に共鳴したから
私は思う。
彼のような人がいたということを、知らないで生きるのはもったいない。
便利さに溺れ、娯楽に流れ、
“何をして生きるか”より、“どう生きたいか”を忘れてしまいがちな今、
船坂さんはその姿で教えてくれる。
命とは、
「尽きるまで捧げる対象があってこそ、輝くのだ」と。
船坂弘さんの人生は、まさに「道」
誰かに教えるためでなく、自ら貫くことで語った人でした。
彼の生き様に心震わせたひとりの人間として、この魂の震えを、未来に渡したいと思ったので記事にしました。
戦わずして気づける私たちは、
もしかしたら、もっと自由に生きていいのかもしれないですね。